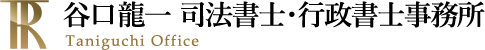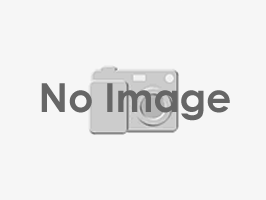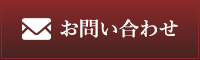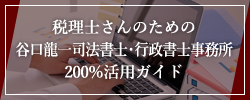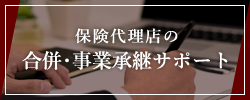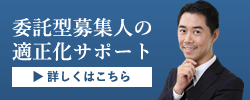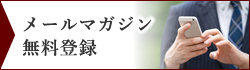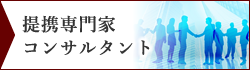コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
相続登記義務化の概要
2026/01/19相続登記義務の内容
相続により不動産を取得した相続人は、
自己のために相続が開始したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
対象となる相続
2024年4月1日 以降 に発生した相続
2024年4月1日 以前 に発生し、未登記のままの相続
→ これらも 2027年3月31日まで に登記が必要(経過措置)
罰則
正当な理由なく相続登記を怠った場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
「放置」が最も危険である理由
相続登記において、実務上もっとも問題となるのは
**「何もしていない状態が長期間続くこと」**です。
① 相続関係が時間とともに複雑化する
相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増える
住所不明・連絡不能の相続人が生じる
遺産分割協議が事実上不可能になる
という事態に陥ります。
結果として、
本来は比較的簡単に済んだはずの相続登記が、調停・訴訟レベルの問題に発展するケースも少なくありません。
② 不動産を「動かせない資産」にしてしまう
相続登記が未了の不動産は、
売却できない
担保に入れられない
有効活用できない
つまり、資産でありながら事実上“凍結”された状態になります。
空き家問題や固定資産税の負担だけが残り、
経済的にも精神的にも重荷になることが多いのが現実です。
③ 相続人間の紛争リスクが高まる
「登記をしていない=権利関係が曖昧」な状態は、
誰が管理するのか
費用負担をどうするのか
売却の可否
といった点で、相続人間の認識のズレを生みやすくなります。
相続登記は、
相続人全員の権利関係を“見える化”し、紛争を未然に防ぐ手続きでもあります。
遺産分割が終わっていない場合でも「何もしなくてよい」わけではありません。
「遺産分割協議がまとまっていないから登記できない」
このようなご相談は非常に多く寄せられます。
しかし、法改正後は「何も対応しない」という選択肢は存在しません。
状況に応じて、
相続人申告登記の活用
段階的な登記対応
将来の遺産分割を見据えた整理
など、現実的な対応策を講じることが重要です。
相続登記は「単なる名義変更」ではありません
相続登記の実務では、
戸籍の精査
相続関係説明図の作成
不動産の権利関係の確認
将来の相続・二次相続の検討
など、法律・実務の両面からの判断が求められます。
形式的に登記を済ませることよりも、
将来に問題を残さない設計ができているかが極めて重要です。
まとめ|「今は困っていない」が一番危ない
相続登記はすでに義務
放置すればするほど、解決コストは増大
早期対応こそが、最も負担の少ない選択
相続登記は、「問題が起きてから」ではなく「問題が起きる前」に行うべき手続きです。
不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐためにも、
相続が発生している、あるいは未登記の不動産がある場合は、
できるだけ早く専門家へご相談ください。一周忌と一回忌の違い
2020/04/16一周忌は、故人が亡くなってから「満1年後」に行われる「法要」の事です
これに対して一回忌は故人が亡くなった「命日」です。
ですから一周忌は二回忌となります。
数え年と満年齢のようなものと考えればわかりやすいでしょうか。
一般的に一周忌までが喪に服す期間とされています。
法要としては「一周忌」「三回忌」「七回忌」「十三回忌」「三十三回忌」があります。
相続手続きはいつまでにしないといけない?
2020/04/14相続のご依頼があった場合、「いつまでに手続きをしなければならないのか?」とのご質問がよくあります。
相続「登記」手続については、法律上の期限はありません。
しかし長期間登記手続を放置しておくと、下記のようなデメリットがあります。
・戸籍等の必要書類の保存期間を経過してしまい書類を取得できず手続きが煩雑になる。
・相続人が死亡して当事者が増えて、話し合いがまとまりにくくなるといったおそれがる。
ですから当事務所では、特別な事情がない場合は、1周忌(亡くなられてから1年後)ぐらいまでには相続「登記」手続きが終わるようにされる事をお勧めしています。
なお、相続「登記」手続については特に期限はありませんが、家庭裁判所でする相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)、所得税の準確定申告(4ヶ月以内)、相続税の申告(10ヶ月以内)等は期限があるのでご注意下さい。印鑑証明書の有効期限は3か月?
2020/04/12実印の登録方法
2020/04/11・登録する印鑑と運転免許証やパスポートなど官公署発行の本人確認書類(顔写真付き)を持参して登録する。
・登録する印鑑、委任状、代理人の印鑑、本人確認書類を持参して登録する。
実印として登録できない印鑑はどのようなもの?
2020/04/08
京都市HPより引用・1人につき1個であること。
・同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。
・住民基本台帳に記録されている氏名等(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表していること(氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの等)。
・印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。
・職業,資格,その他氏名等以外の事項を表していないこと(「○○之印」や「○○之章」は登録可能)。
・印影が鮮明で文字の判読が容易であること。
・ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。
・外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものであること。
・同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。
・その他,区長が不適当と認めるものでないこと。
配偶者居住権を遺言で決める場合の書き方
2020/04/05配偶者居住権が始まりました
2020/04/04自筆証書遺言は封筒に入れて封印をしておかないといけない?
2020/03/31法律で自筆証書遺言として有効になるための条件があります。
したがって自筆証書遺言は封筒に入れて封印をしていなくても大丈夫です。
しかし、変造などがされないようにするために、封筒に入れて封をし、実印で封印することをお勧めしています。
表面に「遺言」と記載し、裏面には作成した年月日を記載し署名・押印されるとよいでしょう。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きのもとで、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければなりません。
遺族が遺言を開封してしまわないように「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておかれるほうがよいでしょう。
公正証書で作った遺言は作り直しは同じ公正証書でないといけない?
2020/03/30
- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740