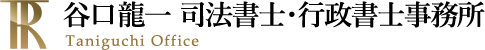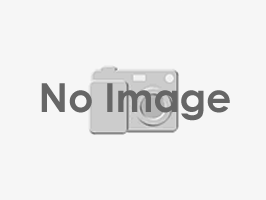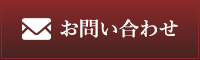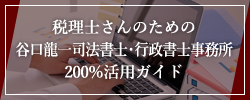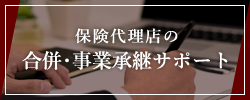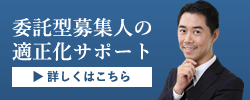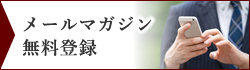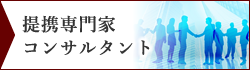コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
遺言書の検認の手続
2012/08/07亡くなった方の遺言書(公正証書遺言書を除く)が見つかった場合、見つけた相続人の方は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「遺言書の検認」の手続きをする必要があります。
この検認の手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を明らかにし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。遺言書の検認の手続きは、遺言書が封筒に入っており封印がされていても、封筒に入っていなくても、必要な手続きです。
もし、遺言書が、封筒に入っており、封印してある場合は、開封してはいけません。
家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いのもと、開封しなければならないことになっているからです。家庭裁判所において開封しなかった場合は、5万円以下の過料(罰金のようなものです)に処される可能性があります。
遺言書の効力については、家庭裁判所において開封しなかった場合でも遺言書が無効となることは、ありません。
尚、この検認の手続きが必要になる遺言書は、「自筆証書遺言書」と、「秘密証書遺言書」です。「公正証書遺言書」については、検認の手続きは、必要ありません。
公正証書遺言書には、遺言書の偽造や変造のおそれがないからです。
検認の申立ての流れについては、家庭裁判所に検認の申立書を提出後、約1ヶ月後に相続人全員に検認期日の通知が送られます。検認の期日に相続人立会いのもと、遺言書の内容を確認するのですが、この立会いは任意なので、申立人以外の相続人の方は、必ず立会わなければならない訳では、ございません(検認手続きの申立人は、必ず立会う必要があります)
立会わなかった相続人の方には、後日、検認手続きが終了した旨の通知が送られます。
検認の手続きが終了すると、遺言書は、検認済証明書と一緒に、申立人に返還されます。
その後、不動産の相続登記をする場合は、この検認済証明書付きの遺言書を使って、登記手続きをすることになります。
遺言書
2012/08/07代表の谷口です。
最近、遺言に関する相談、依頼が多いです。
新聞等で遺言・エンディングノートに関する記事も増えたように思いますし
相続税の改正があると思われるので、その影響でしょうか?
さて、遺言には色々な種類がありますが、一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、当事務所が遺言書作成の相談を受けた場合には、よほどのことがない限り、 改ざん・紛失のそれがなく、検認が不要で相続後の手続が簡単な「公正証書遺言」をお勧めしています。
また場合によっては預金の払い戻しや登記手続を簡単に済ますために、遺言執行者を決められることもお勧めしています。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい。
相続手続の期間
2012/08/07代表の谷口です。
相続のご依頼があった場合、「いつまでに手続きをしなければならないのか?」とのご質問がよくあります。
相続「登記」手続については、法律上の期限はありません。
しかし長期間登記手続を放置しておくと、戸籍等の必要書類の保存期間を経過してしまい書類を取得できず手続きが煩雑になる、あるいは相続人が死亡して当事者が増えて、話し合いがまとまりにくくなるといったおそれがあります。
当事務所では、特別な事情がない場合は、1回忌ぐらいまでには相続「登記」手続きが終わるようにされる事をお勧めしています。
なお、相続「登記」手続については特に期限はありませんが、家庭裁判所でする相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)、所得税の準確定申告(4ヶ月以内)、相続税の申告(10ヶ月以内)等は期限があるのでご注意下さい。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい。

- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740