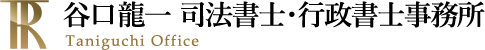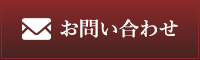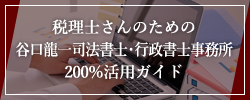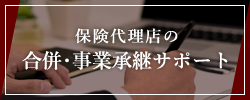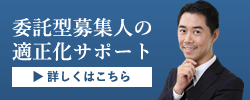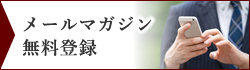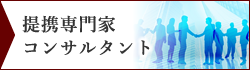- ホーム
- コラム
コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
著作権登録
2012/08/07許認可を担当しております佐藤です。
著作権というと自分で作成した物について後々誰かに真似されないように著作権を取る必要があると思われがちですが、著作権は、自分で作品を作成した段階で自然に発生するものなので、著作権の登録をしなくても作品を作成した時点で著作権を持っていることになります。
一般に言われる著作権の登録というのは、著作権に関する登録のことで、下記のような種類があります。
・実名の登録
・第一発行年月日等の登録
・創作年月日の登録
・著作権・著作隣接権の移転等の登録
・出版権の設定等の登録
著作権に関する登録で保護されるものは、著作物であり、著作権法によると、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)とあります。
要するに、自分の気持ちを表現したものです。作品として表現されたものが著作物として保護されるので、形になっていない方法やアイディアなどは、保護されません。方法やアイディアを保護する為には、特許権や、実用新案権を取得する必要があります。
著作権に関する登録をしておくメリットは、もし作品の発行日において争いがあった場合、作品の創作年月日を登録しておくと、登録されている年月日に作成されたと推定されますし、著作権を譲り受けた人が、第3者との間で著作権の譲渡について争いがあった場合、著作権・著作隣接権の移転等の登録をしておくと、自分が譲渡を受けたと第3者に反論することができます。
要するに著作権に関する登録制度は、第3者との間で争いがあった場合に、登録した人を保護し、反論を容易にする為の制度です。
遺言書の検認の手続
2012/08/07亡くなった方の遺言書(公正証書遺言書を除く)が見つかった場合、見つけた相続人の方は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「遺言書の検認」の手続きをする必要があります。
この検認の手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を明らかにし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。遺言書の検認の手続きは、遺言書が封筒に入っており封印がされていても、封筒に入っていなくても、必要な手続きです。
もし、遺言書が、封筒に入っており、封印してある場合は、開封してはいけません。
家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いのもと、開封しなければならないことになっているからです。家庭裁判所において開封しなかった場合は、5万円以下の過料(罰金のようなものです)に処される可能性があります。
遺言書の効力については、家庭裁判所において開封しなかった場合でも遺言書が無効となることは、ありません。
尚、この検認の手続きが必要になる遺言書は、「自筆証書遺言書」と、「秘密証書遺言書」です。「公正証書遺言書」については、検認の手続きは、必要ありません。
公正証書遺言書には、遺言書の偽造や変造のおそれがないからです。
検認の申立ての流れについては、家庭裁判所に検認の申立書を提出後、約1ヶ月後に相続人全員に検認期日の通知が送られます。検認の期日に相続人立会いのもと、遺言書の内容を確認するのですが、この立会いは任意なので、申立人以外の相続人の方は、必ず立会わなければならない訳では、ございません(検認手続きの申立人は、必ず立会う必要があります)
立会わなかった相続人の方には、後日、検認手続きが終了した旨の通知が送られます。
検認の手続きが終了すると、遺言書は、検認済証明書と一緒に、申立人に返還されます。
その後、不動産の相続登記をする場合は、この検認済証明書付きの遺言書を使って、登記手続きをすることになります。
株式会社設立の注意点(5) 現物出資について
2012/08/07商業登記を主に担当している出口です。
設立において、資本金をいくらにすればよいか悩まれるお客様が多いのですが、「用意できる現金=資本金」にされる方が多いです。しかし、現金があまり用意できない場合でも、「物」で出資することができます。
自動車、機械、パソコン、備品など、出資される方の所有物であれば特に制限はありません。
但し、自動車でまだローンを支払っている場合、通常支払い終わるまでは所有者はローン会社などになっています。この場合はまだ所有者ではないので出資することができません。
自動車の場合は設立後に個人から会社への名義書換、保険の名義変更の手続きが必要となります。
場合によっては個人から法人に所有者が変わることによって、保険料が高くなることもありますので、自動車を出資される場合は、予め保険会社に確認しておいた方がよいでしょう。
不動産の場合も設立後に個人から会社への名義書換が必要になります。
また、担保がついた不動産の場合は色々と検討すべき事がありますので、ご相談下さい。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
ブラックリストについて
2012/08/07債務整理を担当しております佐藤です。
債務整理の相談で、「過払い請求をするとブラックリストに載るのか」、「ブラックリストには、載りたくない」等の相談がよくございます。
まず、ブラックリストが何かについて、ご説明させて頂きます。
ブラックリストとは、まず、クレジットカードやローンを組むことなどによって、顧客情報が、「信用情報機関(過去に延滞などの情報がないかなど調べる為の機関です)」に登録されます。そして、ある一定期間(61日以上といわれています)返済することができなくなってしまった場合は、「事故情報」として「信用情報機関」に登録されます。この登録が、所謂ブラックリストと呼ばれるものです。
また、過払い請求をしてもブラックリストには、載らないと思われます。以前は、完済前に過払い請求をすると、「契約見直し」として、ブラックリストに登録されていましたが、金融庁が、過払い請求をした履歴を信用情報から削除する方針を決めたので、2010年4月19日以降、完済前に過払い請求をしても、ブラックリストには、載らなくなったと思われます。
尚、過払い請求ではなく、任意整理をし、債務が残っている場合は、ブラックリストに登録されます。
そして、その場合、登録抹消までの期間は、各信用情報機関ごとに異なるのですが、任意整理の場合は、5年を越えない期間または、登録日より5年以内とされていることが多く、登録が抹消されるまでの期間は、基本的にはローンを組んだり新しくクレジットカードを作ることが難しくなります(金融会社での審査で、信用情報機関に事故情報があると、審査が通らない場合が多いからです)ですが、信用情報機関での事故情報登録が抹消されないと、絶対にカードは、作れないということもなく、現在の収入状況次第では、カードが作れる金融会社もあるようです。
遺言書
2012/08/07代表の谷口です。
最近、遺言に関する相談、依頼が多いです。
新聞等で遺言・エンディングノートに関する記事も増えたように思いますし
相続税の改正があると思われるので、その影響でしょうか?
さて、遺言には色々な種類がありますが、一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、当事務所が遺言書作成の相談を受けた場合には、よほどのことがない限り、 改ざん・紛失のそれがなく、検認が不要で相続後の手続が簡単な「公正証書遺言」をお勧めしています。
また場合によっては預金の払い戻しや登記手続を簡単に済ますために、遺言執行者を決められることもお勧めしています。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい。
契約書を読んでますか?
2012/08/07代表の谷口です。
契約書にハンコを押す際にはきちんと契約書を読んでいますか?
多くの方が、きちんと読まずに「ここにハンコを押して下さい」といわれるままにハンコを押しているのではないでしょうか?
正直、私も法律や契約に携わる仕事をしていますが、すべての契約書を完全に読んでいるわけではなく、重要な部分だけけしか読んでいないこともあります。
しかし、これはとてもこわい事なんです。
そもそも契約書を作成するのはなぜでしょうか?理由としては、以下の2つがあげられます。
1,契約の内容を証明するため
2,契約前に内容を確認するため
以下、詳しく説明します。
1,契約の内容を証明するため
例えば、お店を借りる契約をした場合で、貸し主が会社であった場合、担当者とは賃料や契約期間、更新料などについて決めていたとしても、担当者が辞めてしまったりした場合や、長期間経ってしまった場合には、自分たちも契約内容を忘れてしまい分からなくなってしまうことが考えられます。
このような場合でも契約書を作成していれば、契約書を見れば内容がすぐに分かります。
このように契約書には後日内容が分からなくなった場合に証拠として利用できます。
2,契約前に内容を確認するため
法律上は契約書を作成しなくても契約は成立します。
しかし契約書という文書にすることにより、言った言わないや勘違いを防ぐことが出来ます。
例えば、お店を借りる契約をする場合で貸し主は「店を使用していい時間は夜の11時まで」と思っていたのに、借り主は「店を使用していい時間は夜の12時まで」と思っていた場合、契約書を作成して、きちんと契約書を読んでいれば、契約をする前に内容が違っているということで、改めて内容を確認することとなり、後日のトラブルを防ぐことが出来ます。
また、思っていなかった契約内容が入っているようなこともあります。
このように、契約書を作り、きちんと読むことによって無用のトラブルを防ぐことが出来るので、契約書はきちんと読みましょう。
会社設立の注意点(4) 会社の目的(事業内容)について
2012/08/07商業登記を担当している出口です。
株式会社設立において、会社の目的(事業内容)を定める必要があります。
通常、目的は主となる業務から順に記載します。建設業、人材派遣業などの許可が必要な業務の場合、目的の記載方法が定められているものがありますので注意が必要です。
どのように記載すればいいか分からないという場合は、事業内容をお伺いし、こちらで目的案を作成致しますのでご相談ください。
また、今すぐにではないけれど、いずれするかもしれないという業務も記載しておくことができます。実際に新しい業務を始める際に目的追加の登記を行っても構わないのですが、登録免許税3万円と専門家に依頼した場合はその費用もかかります。
予定している業務があれば、設立の段階で入れておかれる方がよいでしょう。
但し、実際に行っている業務と関連のない業務が多すぎると、取引先や銀行などが会社の登記簿謄本を見たときに不信感を抱かれる可能性があるので、ご注意下さい。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
忘れがちな登記 法人役員の住所変更
2012/08/07代表の谷口です。
株式会社では代表取締役の住所が登記する事項となっています。
法人の種類によっては代表者以外の役員の住所も登記する事項となっていることがあります。
代表取締役が住所変更した場合には、2週間以内に登記をしなければ、過料(罰金のようなもの)に処されることがあります。(会社法第915条第1項)
会社名(商号)や本店などの場合は、会社名を変えて(株主総会で決議して)いたけれど登記をし忘れていたということは、まずないと思いますが、代表取締役の住所変更は忘れられていることが、たまにありますので、ご注意下さい。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい
古物商の許可について
2012/08/07今回は、古物商の許可について述べさせて頂きたいと思います。
まず、古物についてですが、古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの(例えば、誰かに戴いたが、一度も使用せずに自宅に保管している贈答品などです)又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。これらの古物を買い取って、お店等で販売する場合は、古物商の許可が必要になります。
逆に自分で使用する為に購入した物をオークションなどでネット販売する場合などは、古物商の許可は、不要です。
また、許可を取得する際の要件としては、次のいずれにも該当しないことです。
①成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
②禁錮以上の刑または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
③住居の定まらない者
④古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
⑤営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
古物商の許可申請を提出する際の注意点としては、申請の添付書類として、法人の場合は、会社の登記謄本が必要ですが、謄本の目的の欄に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載がなければ、許可が取れない都道府県と、記載がない場合は、後日変更すれば、申請時には、記載がなくても取れる都道府県があるので、営業所を設けようとする場所を管轄する警察署に確認が必要です。
また、許可は、公安委員会ごとに受ける必要があるので、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けようとする場合は、それぞれの公安委員会に対する許可申請が必要です。
更に古物商の許可を取得した後、次のいづれかに該当した場合、営業停止や許可取消処分となりますので、注意が必要です。
①古物商の許可を受けたのに6ヶ月過ぎても営業を始めない
②営業を開始したものの、6ヶ月以上も休業が続いている
③古物商の商人が、3ヶ月以上も所在不明になっている
以上、古物商許可を取得する際の注意点を中心に述べさせて頂きました。
古物商の許可申請は、要件と書類さえ揃っていれば、申請書の作成自体は、難しくは、ございません。ご不明な点がございましたら、いつでもご相談下さいませ。
会社設立の注意点(3) 本店所在地
2012/08/07商業登記を担当している出口です。
株式会社設立において、賃貸物件を本店として登記する場合は、予め貸主の了解を得ておくことをおすすめします。また、その際はいつから登記を置いてもよいか確認しておきましょう。
特に、会社の設立登記後に賃貸契約を結ばれる場合は注意が必要です。
なぜなら、登記をする時にはまだ借りていない物件を、了解もなく会社の本店として登記すると、他人の所有物件に勝手に登記を置くような形になってしまうからです。貸主によっては気分を害され、契約締結を拒否されるなどのトラブルになることもあります。
賃貸契約を結ぶ前には登記を置かないで欲しいと言われた場合は、賃貸契約を結ぶ時期又は設立登記の申請時期を再検討する必要が出てきますので、早めに確認しておく方がよいでしょう。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。

- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740