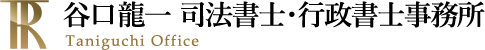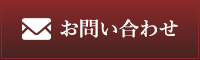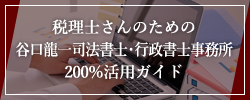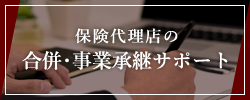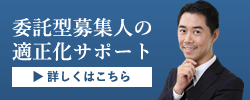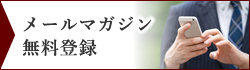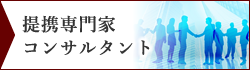コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
建設業許可を考えているなら、書類は大事に保管を!!
2015/06/29建設業を担当している、大掛です。
建設業の許可を取るときに、ネックになる要件として「経営業務の管理責任者」の要件があります。
建設業について取締役や個人事業主として5年〜7年経営経験を要します。
この法律上の要件を実際には満たしているのに、これを証明する裏づけ書類がないが為に
許可を取ることができないという本当に残念な結果になってしまうことがあります。
裏付け書類としては
まず、経営に携わっていた事実を証明するために
会社なら役員としての5〜7年の任期が証明できる登記簿謄本、
個人事業をしていた方は、5〜7年分の確定申告書が必要です。
そして、本当に建設業を行っていたことの証明として
工事の契約書又は注文書と請書のセット等が5〜7年分(各年度に1件以上)必要です。
しかし、契約書があっても工事場所、期間、請負金額等の必要な事項が記載されていないと使えなかったりします。
建設業許可をお考えの方は、これらの書類を大切に保管されるとともに、契約書等の内容も確認して下さい。
当事務所では、契約書等の書類のフォーマットもご準備致しておりますので
「この書類で大丈夫かな?」と思われましたら、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
若年技術者の雇用による経営事項審査の点数アップ
2015/03/13建設業を担当しています大掛です。
平成27年4月1日から経審の審査項目に新しい項目が追加されます。
その1つが若年技術者の雇用状況を評価する項目で、具体的には
・技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が名簿全体の15%以上
・審査基準日から1年以内に新規雇用した35歳未満の技術職員が名簿全体の1%以上
の基準を満たせばそれぞれ一律1点が加点されます。
経審の点数アップをお考えの経営者の皆様、新規雇用をされる際にはこの点も考慮されてはいかがでしょうか?
※技術職員名簿に記載されている技術者とは
1、2級の国家資格を持っているか、10年以上の実務経験がある技術者のことです。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
役員報酬をなしにしたら建設業許可の更新ができないかも
2014/09/08代表の谷口です。
下記のような事例で役員報酬をなしにしてしまうと、常勤性の確認ができず、最悪の場合、更新ができないこともありえます。
税理士さんや社会保険労務士さんは、役員報酬についてご相談を受けることの多いと思いますので、ご注意ください。
A社の代表取締役・経営業務の管理責任者・専任技術者はBさんで、建築一式の建設業許可を4年前に取得しました。
Bさんの息子のCさんは他社で修行していましたが、3年前よりA社に勤務し取締役となりました。
代替わりをしようということで、Bさんは代表取締役から取締役に、Cさんは取締役から代表取締役に変更すると同時にCさんは毎日出勤するものの、役員報酬はなしにしようという手続きを考えています。
建設業許可では、経営業務の管理責任者と専任技術者は常勤でなければなりません。
そして、新規申請や更新の際には常勤性の確認があります。
常勤性の確認は健康保険証・住民税特別徴収税額通知書等で行われます。
上記の事例では役員報酬をなしにすることにより、社会保険から外れることなり、常勤性の確認できる健康保険証等が提出できないことになります。
他の書類でも常勤性の確認ができないとなると、常勤性の要件を確認することが難しくなり、許可の更新ができなくなってしまうおそれがあります。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
建設業許可の更新時期は自分で管理を
2014/07/30代表の谷口です。
建設業許可は5年ごとの更新が必要です。
自動車免許の更新のように、建設業許可の更新については行政から更新の連絡は来ません。
たまに行政が更新時期を教えてくれなかったといって、怒られる方がいらっしゃいますが、更新時期の管理はあくまでご自身でしなければなりません。
また、京都府では建設業許可の更新手続きをする場合の取扱いが平成22年7月1日以降より、従前は求められていなかった確認書類を求められることになり、手続が煩雑になりました。
書類の準備が間に合わないと、最悪のケースでは更新手続きが間に合わず許可が切れてしまい、新たに許可が下りるまで仕事を受注できないということもあり得ます。
ですから、更新時期をきちんと管理し、早くから更新の準備をされた方がよいでしょう。
当事務所では、更新の3−4ヶ月前程度から準備されることをお勧めしております。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
一人親方も労災に加入しましょう
2014/02/07代表の谷口です。
事業主は、通常、労災には加入できないのですが、一人親方は労働者に近い立場ということで、労災に加入することができます。
最近では、一人親方は、労働保険事務組合の労災に加入をして加入員証を提示しないと、現場への出入りができないことがあります。
なお、労災の手続については、社会保険労務士さんの分野となりますので、加入をお考えの方は当事務所と提携している社会保険労務士さんをご紹介致します。
建設業許可の決算変更届を毎年提出してますか?
2013/10/01代表の谷口です。
建設業許可を受けた建設業者は、決算から4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。提出を怠った場合、罰則もあります。
また5年に1度の建設業の更新の際には、決算変更届が5年分全てが提出されていなければなりません。
ただ、実際には毎年提出をされていない場合も、少なくありません。
決算変更届の提出を放置していると、5年に一度の更新の際に一度に5年分の決算変更届をしなければなりません。
決算変更届には、工事経歴書というその年の主な工事の名称、場所、注文主、請負代金等を10件程度記載しなければなりません。
5年分まとめて決算変更届をするということは、5年分の工事の一覧表を作成しなければならないことになります。
5年前にどの様な工事をしかたなどをリストアップするのは面倒だと思われます。
また、行政書士に依頼された場合、報酬も5年分を一度にまとめての支払うとなると、費用面の負担も大きいと思われます。
ですから、「確定申告が終わったら次は建設業の決算変更届」というように、毎年決算変更届をすることをお勧めします。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
法人成りをした場合、建設業の許可は個人から法人に引き継げるか?
2013/07/01Aさんは、個人で建設業を営んでいた時に、建設業の許可を取得しました。
今回、新しく会社を設立しようと考えています。
建設業の許可は、個人の時に取得しているので、新しく設立した会社でも、この許可を引き継ぐことはできるでしょうか?
この場合、許可の引き継ぎは出来ません。
なぜなら、建設業の許可は、個人事業主であるAさんに対して許可されたからです。
したがって、新しく会社を設立した場合、会社で新しく建設業の許可を申請し、個人の時に取得した許可は、廃業届を申請する必要がございます。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
建設業の実務経験10年のみで2業種の許可が取得できるか?
2013/05/21Aさんは、10年間、大工工事と左官工事をしていました。各工事とも国家資格は持っていません。実務経験10年間のみでAさんが専任技術者として、大工工事と官工事の2業種の許可が取得できるか?
上記のケースでは、2業種の許可は取得できません。
Aさん1人で大工工事と左官工事の実務経験を証明する場合、重複する期間は、1業種分しか認められないので、
大工工事及び左官工事について国家資格を持っておらず、実務経験が10年しかないAさんは、
大工工事または左官工事のどちらか1つの工事しか許可を取得することができません。
Aさん1人が専任技術者として実務経験のみで2業種を担当する場合は、20年の実務経験が必要になります。
大工工事、左官工事両方の許可を取得したい場合は、下記の方法等が考えられます。
○先に大工工事で許可を申請しておき、10年後に左官工事で許可を申請する。
○先に大工工事で許可を申請しておき、左官工事の国家資格を取得出来次第、左官工事の許可を申請する。
○左官工事について10年間の実務経験がある人、又は左官工事について国家資格を持っている人を雇用した上で、Aさんが大工工事の専任技術者、新しく雇用した人を左官工事の専任技術者として申請する。
京都の建設業許可申請について
2012/08/27京都で建設業の新規許可・更新手続きをする場合の取扱いが平成22年7月1日以降より、従前は求められていなかった確認書類を求められることになりました。
専任技術者が、10年の実務経験ありとして、許可を取得する場合、実務経験期間中の在籍確認書類を提示する必要があります。
在籍確認として提示する書類としては、年金の被保険者記録照会回答票がありますが、年金の被保険者記録照会回答票だけで在籍の確認ができない場合は、その補完資料として日報、賃金台帳や、出勤簿等の提示を求められる場合があります。
尚、在籍確認は、個人事業主であった期間は、省略することができます。
また、経営業務の管理責任者や、専任技術者の常勤性確認として、住民票の他に、健康保険被保険者証などが必要なのですが、経営業務の管理責任者及び専任技術者が、実際会社に常勤していることが証明できなければなりませんので、保険者証に会社名の記載がない国民健康保険の保険証は、添付書類としては認められません。
国民健康保険の保険証しかない場合は、源泉徴収簿及び領収済通知書又は、出金簿及び賃金台帳が必要になります。
京都で建設業の許可を取得しようとする場合、平成22年7月1日以降より、提示する書類が増えて、許可申請が以前に比べて手間取るようになりました。
これから京都で許可を取得される予定の方は、在籍確認が証明できるような書類を作成しておくか、残しておいた方がよいかと思います。
建設業法施行規則と建設業法第27条の23第3項の一部改正
2012/08/07建設業法施行規則の一部と建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部が改正されました。改正内容は、下記のとおりです。
① 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化(平成24年7月1日施行)※経営事項審査の際、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険に未加入の場合、それぞれ40点の減点(雇用保険、厚生年金保険及び健康保険全てに未加入の場合120点の減点)
② 建設業の許可申請及び許可更新時の添付書類として、保険の加入状況を記載した書面の提出(平成24年11月1日施行)
③ 施行体制台帳に、保険加入状況を記載(平成24年11月1日施行)
※施行体制台帳とは、特定建設業者が、工事を元請で請負った場合で、下請契約の請負代金の額が3,000万円以上になるときは、下請負人の商号又は名称、建設工事の内容及び工期等を記載し、工事現場ごとに備え置く必要のあるものです。
上記の改正により、建設業の許可を申請する際には、保険加入状況を記載した書面を求められることになり、もし、未加入だった場合は、許可を行うと同時に保険に入るよう文書にて指導されます。そして、指導後尚未加入の場合は、保険担当部局(健康保険、年金なら年金事務所、雇用保険なら地方労働局)に通報されることになります。
この改正に至る背景には、これまで建設業界では、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を負担しない保険未加入企業の存在があり、法律を守り、適正に法定福利費を負担する企業が、保険未加入企業と比べて、競争上不利になったり、又、保険未加入だと、公的保障が受けられない為、保険未加入が、建設業界の就職人数減少の一因となっていました。
そこで、これら是正の為、社会保険未加入問題に対し、上記改正内容の対策が取られました。
今回の改正で対象になるのは、保険に入る必要があるのに、未加入の会社の場合であり、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険等保険の適用除外で、今まで入っていなかった方は、今まで通り入る必要はこざいません。
建設業については、こちらをご覧下さい。

- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740