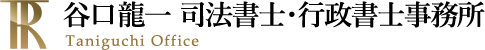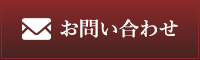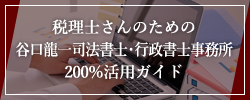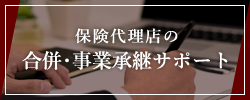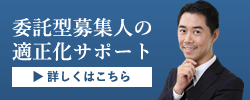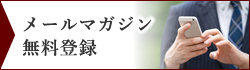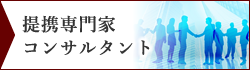コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
株式会社設立の注意点(5) 現物出資について
2012/08/07商業登記を主に担当している出口です。
設立において、資本金をいくらにすればよいか悩まれるお客様が多いのですが、「用意できる現金=資本金」にされる方が多いです。しかし、現金があまり用意できない場合でも、「物」で出資することができます。
自動車、機械、パソコン、備品など、出資される方の所有物であれば特に制限はありません。
但し、自動車でまだローンを支払っている場合、通常支払い終わるまでは所有者はローン会社などになっています。この場合はまだ所有者ではないので出資することができません。
自動車の場合は設立後に個人から会社への名義書換、保険の名義変更の手続きが必要となります。
場合によっては個人から法人に所有者が変わることによって、保険料が高くなることもありますので、自動車を出資される場合は、予め保険会社に確認しておいた方がよいでしょう。
不動産の場合も設立後に個人から会社への名義書換が必要になります。
また、担保がついた不動産の場合は色々と検討すべき事がありますので、ご相談下さい。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
会社設立の注意点(4) 会社の目的(事業内容)について
2012/08/07商業登記を担当している出口です。
株式会社設立において、会社の目的(事業内容)を定める必要があります。
通常、目的は主となる業務から順に記載します。建設業、人材派遣業などの許可が必要な業務の場合、目的の記載方法が定められているものがありますので注意が必要です。
どのように記載すればいいか分からないという場合は、事業内容をお伺いし、こちらで目的案を作成致しますのでご相談ください。
また、今すぐにではないけれど、いずれするかもしれないという業務も記載しておくことができます。実際に新しい業務を始める際に目的追加の登記を行っても構わないのですが、登録免許税3万円と専門家に依頼した場合はその費用もかかります。
予定している業務があれば、設立の段階で入れておかれる方がよいでしょう。
但し、実際に行っている業務と関連のない業務が多すぎると、取引先や銀行などが会社の登記簿謄本を見たときに不信感を抱かれる可能性があるので、ご注意下さい。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
会社設立の注意点(3) 本店所在地
2012/08/07商業登記を担当している出口です。
株式会社設立において、賃貸物件を本店として登記する場合は、予め貸主の了解を得ておくことをおすすめします。また、その際はいつから登記を置いてもよいか確認しておきましょう。
特に、会社の設立登記後に賃貸契約を結ばれる場合は注意が必要です。
なぜなら、登記をする時にはまだ借りていない物件を、了解もなく会社の本店として登記すると、他人の所有物件に勝手に登記を置くような形になってしまうからです。貸主によっては気分を害され、契約締結を拒否されるなどのトラブルになることもあります。
賃貸契約を結ぶ前には登記を置かないで欲しいと言われた場合は、賃貸契約を結ぶ時期又は設立登記の申請時期を再検討する必要が出てきますので、早めに確認しておく方がよいでしょう。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
株式会社設立の注意点(2)役員構成
2012/08/07商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。
お客様から「株式会社を設立したい。役員は身内のみで4名にしたい。」と相談があった場合、どのような役員構成が考えられるでしょうか?
一般的には下記のような役員構成で検討することが多いかと思います。
① 取締役会は置かず、取締役4名 監査役は置かない
② 取締役会は置かず、取締役3名 監査役1名
③ 取締役会を置き、取締役3名 監査役1名
当事務所では、①か②をお薦めしています。
なぜなら、取締役会を置いた場合、最低でも取締役3名以上、監査役1名以上が必要と定められているため、常に役員を4名以上置く必要があるからです。
設立当初は問題がなくても、時間が経ち、役員が辞めたり、亡くなられたりした場合、新しく役員になってもらう方を探すのが難しいこともあります。
もちろん、③の場合でも取締役会を廃止すれば、4名以上置く必要は無くなりますが、役員の辞任等と共にに登記する場合、登録免許税が最低でも4万円必要となります。株式の譲渡制限の承認機関を「取締役会」にしている場合は、その変更も必要となるため、更に3万円必要となります。
その点、①②の取締役会を置かない場合は、役員変更の登録免許税1万円で足りることになります。
大きな会社では、株主総会を開かずに取締役会で決議することができるメリットは大きいかと思いますが、中小企業で株主が少数の場合、取締役会を置くメリットは少ないのではないでしょうか。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
株式会社設立の注意点(1)類似商号・会社名
2012/08/07代表の谷口です。
旧商法19条では、同一市町村で類似した会社名で同一の目的(事業内容)の会社設立は禁止されていました。
しかし、現在の企業活動の広がりや類似商号に該当するかどうかの判断が難しいなどの理由により、類似商号禁止規定は廃止されました。
ただ、同一本店で同一会社名が複数存在するのは適当ではないため、目的(事業内容)が異なっていたとしても、同一本店・同一商号の登記は出来ません。(商業登記法第27条)
このように類似商号規制は廃止されましたが、不正競争防止法による「不正競争」に当たる行為の規制は今までと同じくあります。
したがって今後も、場合によっては似た会社名の会社がないかの調査はする方がよいでしょう。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。

- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740