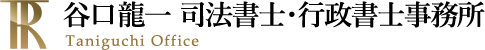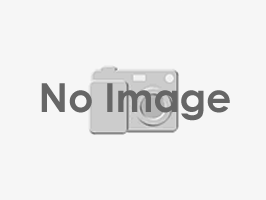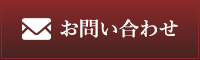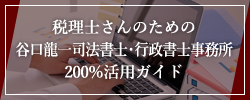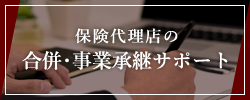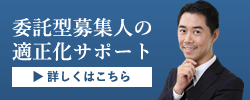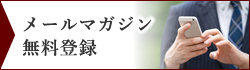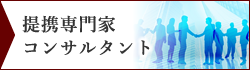コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
法人の印鑑証明書は代表者でないと取れない?
2019/11/18法人の印鑑証明書は大切な書類であることから、代表者本人が法務局に行かないと取れないと思われている方も少なからずいらっしゃいます。
しかしながら、法務局から発行されている法人の印鑑カードを持参すれば代表者本人でなくても、家族や従業員、司法書士などでも取得することが出来ます。
ただし、取得の際に代表者の生年月日を記載、入力しなければならないので、印鑑証明書を取りに行かれる方には代表者の生年月日をお伝えください。
許認可を持ってる会社の本店移転
2019/03/07各種許認可では本店(事務所)が一定の要件を満たしていることが必要となる場合が多いです。
例えば、居住用でなく事務所用(事業用)であること、自社の関連会社を含めて他社と共同で使用しないこと、一定の面積があること、駐車場まで一定以内の距離であること等です。
本店(事務所)を移転される場合、許認可をもっている場合には新たな本店(事務所)が許認可の要件を満たしているかを確認したうえで移転されることをお勧めします。
会社の株を譲渡する場合、法務局に申請が必要?
2018/11/09登記がいつ出来るかの確認方法
2018/11/08登記事項証明書(登記簿謄本)は登記申請中は取れません
2018/10/25登記申請をして完了するには時期等にもよりますが1週間程度の期間を要します。
この間は登記事項証明書は取れません。
これは登記は受理された時点で効力が生じるので、もし登記申請中に登記が完了する前の状態の証明書を発行してしまうと正しい証明が出来ないことになるからです。
会社や法人の証明書が融資の申し込みや色々な契約の際に必要です。
登記申請をしてから実は証明書が必要だったのに取れないということがないように、当事務所では登記申請する前に証明書が必要ないかを依頼者に確認するようにし、証明書が必要であれば登記申請をする前に取得するようにしております。
協会を立ち上げるなら一般社団法人がお勧めです
2018/10/16会社の登記懈怠の過料は代表者個人にかかります
2015/06/29商業登記を主に担当している出口です。
会社の登記は、原則変更があってから2週間以内に登記する必要があり、登記が遅れると過料がかかってくる可能性があります。
今までも何度か、代表者の住所変更の登記や役員の死亡の登記が忘れがちですのでお気を付けくださいというお話をさせて頂きました。その他には結婚して名字が変わった場合なども忘れがちかと思います。
実際に過料が科される場合の流れは下記のようになります。
登記申請
↓
登記官が懈怠に気付き、裁判所へ通知
↓
裁判所で過料を科すかどうか、科す場合はその金額を決定
↓
過料が科される場合、代表者の自宅に裁判所から過料の通知が届く
この過料は会社ではなく、代表取締役個人に対してかかりますので、会社の経費、損金にはなりません。
また、行政罰なので前科はつきませんが、過料を科された影響で勲章の授与を受けられなかったという話を聞いたことがあります。
監査役の会計監査限定の登記が必要になりました
2015/06/29商業登記を主に担当している出口です。
平成27年5月1日、会社法の改正があり、監査役の会計監査限定の登記が必要になりました。下記に該当する場合は登記が必要になりますのでご注意ください。
定款に「監査役の権限を会計監査に限定する」旨の文言が入っている
平成18年5月1日の会社法施行時に小会社(資本金が1億円以下で、負債総額が200億円未満の会社)で、かつ、全ての株式につき譲渡制限がある会社
(監査役会、会計監査人設置会社を除く)
なお、この登記は平成27年5月1日以降で、最初に監査役に関する変更登記を行うときに併せて行えばよいことになっており、併せて行う場合は登録免許税は別途かかりません。
役員の死亡による退任登記をお忘れなく
2015/04/28商業登記を主に担当している出口です。
当事務所では役員変更登記をよくご依頼頂くのですが、下記のようなやりとりを何度かさせて頂いたことがあります。
お客様「役員は全員再任でお願いします。」
出口「かしこまりました。(登記簿を見ながら)取締役A、B、C、Dが再任ですね。」
お客様「あ、Aはもう数年前に亡くなっています。」
意外に思われるかもしれませんが、死亡による退任登記がされていないことがときどきあります。代表者はその方が亡くなられた事は知っているのですが、役員として入っている、あるいは退任登記をしないといけないという意識が無いようです。
例えば、代替わりをして代表取締役は子に変更しているが、平取締役として親が残っていて亡くなられた場合など、役員として名前は残っているけれども、実際はほとんど業務に携わっていない方である場合が多いです。
取締役、監査役が亡くなられた場合は、死亡から2週間以内に退任登記をする必要がございます。登記が遅れれば、過料(罰金)がかかってくることがございますので、お早めにお手続きされることをおすすめ致します。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
代表取締役変更の決議ができない場合
2015/04/23商業登記を主に担当している出口です。
4月1日から新代表者に代わるというのはよくある事かと思います。ではそれが決まるのはいつ頃でしょうか。通常、数ヶ月前には会社内部で決まっているのではないでしょうか。但し、実際に新代表者に就任するには、当然選任決議が必要です。
就任日より前に代表取締役の予選決議を行う場合で、決議機関が「取締役会」や「取締役の互選」の場合、有効に決議を行うには条件があります。それは、取締役全員に変動がなく、かつ、就任前一ヶ月以内程度であることです。
つまり、下記のような場合は予選ができません。
2月の取締役会で4月1日からの新代表取締役を予選する
→ 一ヶ月以上前なので不可
3月31日時点で現代表取締役が役員を退き、4月1日から新代表取締役が就任する
→ 予選決議のときから取締役が減っているから不可
予選決議の後、新代表取締役の就任前に新しい平取締役が就任した
→ 予選決議のときから取締役が増えているから不可
就任日より前に選任決議をされる場合はご注意ください。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。

- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740